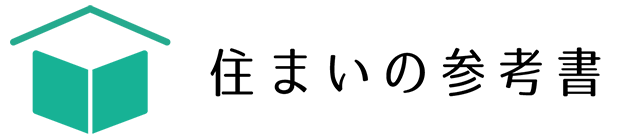断熱の基準
断熱基準の始まりは昭和55年
住宅には、断熱工事がつきものですが、どのような基準で断熱をするのでしょうか。
もちろん、断熱をすることによって、冷暖房費などが少なくてすむことは当たり前のことですが、昭和55年に施行された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」という法律が住宅断熱化のスタートでした。
その後、住宅水準の急速な向上や、エネルギー消費量の予想以上の上昇、地球規模の温暖化問題や、平成9年の京都議定書が採択されたことなどを受けて、平成11年までに3回にわたって改訂され、当時、「省エネルギー対策等級」として、それぞれの年度に改訂された断熱基準が等級のランクになっていました。
時代の変化とともに改正されていった、それぞれの時期の法律の内容が、昭和55年の法律は、「旧省エネルギー仕様」となり、平成4年の法律は「新省エネルギーの仕様」となり、平成11年に改訂された法律の仕様が、当時「次世代省エネルギー仕様」と呼ばれました。
現在は平成28年基準「断熱等性能等級4」
その後、平成25年に等級4の「次世代省エネルギー基準」は、計算式を含めて基準が見直され、「断熱等性能等級」という名称に変わり、新たに「一時エネルギー消費量等級」という基準も追加されるようになりました。
そして、平成28年に小改正が行われ、「改正28年基準」が現在の省エネ住宅=「断熱等性能等級4」となっています。
「ZEH住宅基準」が加わる
さらに近年では、住宅が使用する一次エネルギー消費量ゼロを目指した「ZEH住宅(ゼッチ住宅、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の基準も作られ、政府は2030年頃には、住宅の半分を「「ZEH住宅」にしようと考えているようです。
省エネ化は総力戦・・新たなZEH基準
昭和55年から始まった住宅の省エネ化は、最初は建物の断熱材だけの基準から始まり、平成25年の改訂で、新たに「一次エネルギー消費量等級」ができました。建物の高断熱化だけで無く、住宅設備の省エネ化が評価の対象に加わりました。
そして、新たなZEH基準では、創エネルギーとして、「蓄電装置、燃料電池、太陽利用熱温水システムの設置」など建物以外のエネルギーの再利用の要素も加えて住宅の一次エネルギー消費量のゼロ化が計られています。
注:一次エネルギーとは、自然界から得られた加工しないエネルギーのことで、一次エネルギー消費量のゼロ化は、光熱費のゼロ化と直接的なイコールではありません。
令和3年4月より、断熱性能の説明義務化
地球温暖化対策のため、建物のいっそうの省エネ化が求められるようになり、住宅でも延床面積 300㎡以上の住宅は、断熱等級4の省エネ住宅とするように義務化されました。
300㎡を下回る一般の戸建て住宅では、そのような規制はありませんが、令和3年4月からは、設計者または住宅会社は、設計しようとする、あるいは販売する新築住宅の断熱性能について書面で説明する義務が課されています。
断熱で使う記号
K値(熱貫流率)
熱が、材料を通して温度の高い空間から低い空間へ伝わる現象を熱貫流といい、そのときの「熱の伝わりやすさ」を表す数値を熱貫流率といい、この数値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高いということになります。
断熱性能の基準では、天井や壁、床といった部分ごとに熱貫流率の基準が設けられており、たとえば省エネルギー仕様のⅣ地域の木造住宅の壁の熱貫流率は0.8以下となっています。グラスウール10Kの製品で必要な厚みを求めると右のような式で求めることができます。
UA値(外皮平均熱貫流率)
床面を含む断熱材に覆われた部分の表面積で、具体的には床下断熱や外壁、あるいは天井や屋根断熱の表面積を合計したものです。
これは従来のQ値では、吹き抜けや小屋裏収納など床面積に含まれない部分が多い建物ほど正確なQ値にならないという制度設計上の不備を修正し、より実態に即した計算式になりました。
ηA値(冷房期の平均日射取得率)
上のUA値を建物内から熱が逃げていく方の基準と考えれば、ηA値は、建物に侵入する日射熱の限度を決める基準です。
Q値(熱損失係数 )・・旧基準です
室内外の温度差1℃のとき、住まい全体から1時間に床面積1m2当たりに逃げていく熱量を指し、数字が小さいほど高断熱となります。
次世代省エネルギーの基本となる数値で、屋根、天井、外壁、窓、床、換気などから逃げていく熱の量を延床面積で割ったもの。 逃げていく熱量は、熱貫流率K値を、それぞれの部位で計算することになります。
この数値は地域ごとに決められており、平成25年の法改正までの次世代省エネルギー仕様の代表的な指標の一つでした。
C値(隙間相当面積)・・旧基準です
建物の床面積1m2当たりのすきま面積のことで、延床面積120m2の建物のすきま相当面積は、C値2.0の場合、建物全体で240cm2存在すると言うことです。その結果、C値が小さいほど気密性は高くなり、エネルギーロスも少なくなります。
ただ、建物の気密化が進んだため、C値の優劣を考える必要がなくなり、現在では基準値としては用いられていません。